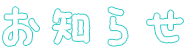【報告】遊び場づくりで「つながる」能登半島ミーティング を開催しました当協会はこれまで大きな災害が発生した際に、遊びを通じた子どもの心のケアを目的として、被災地において子どもたちがいきいきと遊べる場所づくりの支援も行ってきました。このたび、能登半島での支援活動の一環として、被災地で子どもの居場所づくり・遊び場づくりに取り組んでいる活動団体や自治体職員の皆さんが顔を合わせ、情報を共有し、今後の連携を深めるきっかけ、「出会い、知り合い、つながる」ことを目的とした交流の場を輪島市のNOTOMORIにて開催しました。
当日は17の団体・自治体から27人(当協会も含む)に参加いただき、古瀬ワークショップデザイン事務所 代表の古瀬さんのファシリテートのもと、各団体の活動紹介と対話の時間を持ちました。
参加者からは「能登の子どもたちのために(しかも「遊び」という切り口に絞っても)関わられる方がこんなにいることに驚きと嬉しさがありました。」「これまで点ではつながっていても、一堂に介したことがなかったので、全体で集まることの意義を感じた。民間、行政など立場の垣根を超えてみんなで能登で子どもたちの遊び場・居場所を保障しようと共通認識が持てたと感じた。」といった感想をいただきました。
また、閉会の挨拶で企画からご協力をいただいた一般社団法人みらいのともしびの木村さんより「思いを持っている人がこれだけいることが宝。こうやって繋がって、また何か面白いことが起きたら、それが復興につながる」との総括をいただきました。
今後も能登半島で活動する団体の皆さんを支援する形で、少しでも被災地の子どもの心のケアにつながる活動を行なっていきます。
代表 関戸 博樹より
能登半島における地震および豪雨災害により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。また、被災地域において子どもが遊び育つこと、そして震災や豪雨災害で傷ついた心を癒すことを支え続けてきたみなさんが忙しい日々の中で時間を作って私たちが企画した集いの場に足を運んでくれたことに感謝します。集ったみなさんが互いの活動の話をしたり聴いたりする中で、大変だった気持ちややっていて良かった気持ちを一度立ち止まって噛みしめたり、改めて自身の活動を客観的に捉え直す機会になったのではないかと思います。なにより、この地に自分たち以外にも子どもたちの遊び場や居場所をつくろうという志を持った仲間がこれだけいたという事実に、緊張し続けていた気持ちがほぐれたり、モチベーションが上がったりしながら交流の熱が収束しないあっという間の時間となりました。この企画を実施するにあたりご協力いただいた大東建託グループみらい基金にも厚く御礼申し上げます。遊ぶことは子どもにとって生きることそのものであり、それは平時であっても被災している状態であっても変わりません。今後も当会として、出来得る支援のかたちを模索し、能登半島のみなさんの取り組みに伴走していきたいと思っております。
【開催概要】
《日 時》2025年2月23日(日)14:00〜17:30
《会 場》のと里山空港仮設飲食店街NOTOMORI
《対 象》能登地方の被災地において子どもの居場所づくり・遊び場づくりに取り組んでいる活動団体や自治体
《参加者数》27人
《主 催》NPO法人日本冒険遊び場づくり協会
《企画協力》古瀬ワークショップデザイン事務所、一般社団法人みらいのともしび、一般社団法人プレーワーカーズ
《助 成》大東建託グループみらい基金
《内 容》ファシリテーター:古瀬ワークショップデザイン事務所 代表 古瀬 正也 氏
・開会
・スタンドアップ(アイスブレイク)
・知り合う(9マス自己紹介)
・共有したいお話①「子どもの遊び場の意義って?」日本冒険遊び場づくり協会 関戸 博樹
・共有したいお話②「能登半島地震を受けての子どもたちの声」
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 田代 光恵さん
・参加団体活動紹介
・語りおろし
・閉会










ファシリテーターの古瀬さんの総括・感想をご紹介します。写真と共に当日の熱量を感じていただけるかと思います。

前半は、全体で知り合うところから、グループで知り合って、共有したいお話を短く2つほど。
後半は、各団体からの活動紹介を最大3枚の写真を見せてもらいながら、お話いただきました。
13団体ほどあったので、基本は「2〜3分で」としていましたが、想い溢れて「6分ほど」お話される方もおられました。
でも、僕は、止められませんでした。
いや、もっと正確に言えば、意志を持って止めなかったし、止めたくもありませんでした。
もちろん、こういう発表の場面で、きっちり時間を測ってやることもありますし、それが大事な時もあります。
ただ、今回は【出会い・知り合い・つながる】ことが目的の場。
時間厳守で、合理的に、機械的に、進めるのは、どうも似合わないな、と思ったのです。
結果(当然ですが)予定から約30分もオーバーすることになりました。
でも、それは必然で、今ここにいる人たちの想いの集積が、そのような状況を生み出していったのです。
でも、僕は悩みます。
・最後のワーク「語りおろし」をやめるか
・もっと短くできる違うワークに切り替えるか
・短い「語りおろし」に変えて、終了時間をずらすか
終了後には、懇親会が控えている。でも、ほどんどの人が参加するみたい。あとは、その場の空気を感じながら、最後は、自分自身の内なる直感に身を委ねて...
最終的には、3つ目の【短い「語りおろし」に変えて、終了時間をずらす】という選択を取ったのでした。
結果、そのまま30分オーバーで終えましたが、
短い時間でも大いに盛り上がり、また、お互いの【困りごと・悩みごと・課題】を分かち合えたことで、場全体がぐっと深まるのも感じられました。
「もっと話したい」「もっと聞きたい」「もっと繋がりたい」という欲求がピークに高まった状態でワークショップは終わり、
自由な立食形式の懇親会に突入。
懇親会も大盛りあがりで、小さなグループが生まれては、くっついたり、離れたりを繰り返しながら、自由な対話を通して、自然と繋がっていく様子が見られました。
その様子を眺めながら、ああ、この景色が見たかったんだよな...と感じていました。
震災後、この分野で全体的に横で繋がるという動きは少なかったそうなので、今回、このような【出会い・知り合い・つながる】場をつくることに関われて、よかったなと思います。
当協会はこれまで大きな災害が発生した際に、遊びを通じた子どもの心のケアを目的として、被災地において子どもたちがいきいきと遊べる場所づくりの支援も行ってきました。このたび、能登半島での支援活動の一環として、被災地で子どもの居場所づくり・遊び場づくりに取り組んでいる活動団体や自治体職員の皆さんが顔を合わせ、情報を共有し、今後の連携を深めるきっかけ、「出会い、知り合い、つながる」ことを目的とした交流の場を輪島市のNOTOMORIにて開催しました。
当日は17の団体・自治体から27人(当協会も含む)に参加いただき、古瀬ワークショップデザイン事務所 代表の古瀬さんのファシリテートのもと、各団体の活動紹介と対話の時間を持ちました。
参加者からは「能登の子どもたちのために(しかも「遊び」という切り口に絞っても)関わられる方がこんなにいることに驚きと嬉しさがありました。」「これまで点ではつながっていても、一堂に介したことがなかったので、全体で集まることの意義を感じた。民間、行政など立場の垣根を超えてみんなで能登で子どもたちの遊び場・居場所を保障しようと共通認識が持てたと感じた。」といった感想をいただきました。
また、閉会の挨拶で企画からご協力をいただいた一般社団法人みらいのともしびの木村さんより「思いを持っている人がこれだけいることが宝。こうやって繋がって、また何か面白いことが起きたら、それが復興につながる」との総括をいただきました。
今後も能登半島で活動する団体の皆さんを支援する形で、少しでも被災地の子どもの心のケアにつながる活動を行なっていきます。
代表 関戸 博樹より
能登半島における地震および豪雨災害により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。また、被災地域において子どもが遊び育つこと、そして震災や豪雨災害で傷ついた心を癒すことを支え続けてきたみなさんが忙しい日々の中で時間を作って私たちが企画した集いの場に足を運んでくれたことに感謝します。集ったみなさんが互いの活動の話をしたり聴いたりする中で、大変だった気持ちややっていて良かった気持ちを一度立ち止まって噛みしめたり、改めて自身の活動を客観的に捉え直す機会になったのではないかと思います。なにより、この地に自分たち以外にも子どもたちの遊び場や居場所をつくろうという志を持った仲間がこれだけいたという事実に、緊張し続けていた気持ちがほぐれたり、モチベーションが上がったりしながら交流の熱が収束しないあっという間の時間となりました。この企画を実施するにあたりご協力いただいた大東建託グループみらい基金にも厚く御礼申し上げます。遊ぶことは子どもにとって生きることそのものであり、それは平時であっても被災している状態であっても変わりません。今後も当会として、出来得る支援のかたちを模索し、能登半島のみなさんの取り組みに伴走していきたいと思っております。
【開催概要】
《日 時》2025年2月23日(日)14:00〜17:30
《会 場》のと里山空港仮設飲食店街NOTOMORI
《対 象》能登地方の被災地において子どもの居場所づくり・遊び場づくりに取り組んでいる活動団体や自治体
《参加者数》27人
《主 催》NPO法人日本冒険遊び場づくり協会
《企画協力》古瀬ワークショップデザイン事務所、一般社団法人みらいのともしび、一般社団法人プレーワーカーズ
《助 成》大東建託グループみらい基金
《内 容》ファシリテーター:古瀬ワークショップデザイン事務所 代表 古瀬 正也 氏
・開会
・スタンドアップ(アイスブレイク)
・知り合う(9マス自己紹介)
・共有したいお話①「子どもの遊び場の意義って?」日本冒険遊び場づくり協会 関戸 博樹
・共有したいお話②「能登半島地震を受けての子どもたちの声」
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 田代 光恵さん
・参加団体活動紹介
・語りおろし
・閉会










ファシリテーターの古瀬さんの総括・感想をご紹介します。写真と共に当日の熱量を感じていただけるかと思います。

前半は、全体で知り合うところから、グループで知り合って、共有したいお話を短く2つほど。
後半は、各団体からの活動紹介を最大3枚の写真を見せてもらいながら、お話いただきました。
13団体ほどあったので、基本は「2〜3分で」としていましたが、想い溢れて「6分ほど」お話される方もおられました。
でも、僕は、止められませんでした。
いや、もっと正確に言えば、意志を持って止めなかったし、止めたくもありませんでした。
もちろん、こういう発表の場面で、きっちり時間を測ってやることもありますし、それが大事な時もあります。
ただ、今回は【出会い・知り合い・つながる】ことが目的の場。
時間厳守で、合理的に、機械的に、進めるのは、どうも似合わないな、と思ったのです。
結果(当然ですが)予定から約30分もオーバーすることになりました。
でも、それは必然で、今ここにいる人たちの想いの集積が、そのような状況を生み出していったのです。
でも、僕は悩みます。
・最後のワーク「語りおろし」をやめるか
・もっと短くできる違うワークに切り替えるか
・短い「語りおろし」に変えて、終了時間をずらすか
終了後には、懇親会が控えている。でも、ほどんどの人が参加するみたい。あとは、その場の空気を感じながら、最後は、自分自身の内なる直感に身を委ねて...
最終的には、3つ目の【短い「語りおろし」に変えて、終了時間をずらす】という選択を取ったのでした。
結果、そのまま30分オーバーで終えましたが、
短い時間でも大いに盛り上がり、また、お互いの【困りごと・悩みごと・課題】を分かち合えたことで、場全体がぐっと深まるのも感じられました。
「もっと話したい」「もっと聞きたい」「もっと繋がりたい」という欲求がピークに高まった状態でワークショップは終わり、
自由な立食形式の懇親会に突入。
懇親会も大盛りあがりで、小さなグループが生まれては、くっついたり、離れたりを繰り返しながら、自由な対話を通して、自然と繋がっていく様子が見られました。
その様子を眺めながら、ああ、この景色が見たかったんだよな...と感じていました。
震災後、この分野で全体的に横で繋がるという動きは少なかったそうなので、今回、このような【出会い・知り合い・つながる】場をつくることに関われて、よかったなと思います。